みんなの笑顔のための『遺言書のススメ』
遺言とは、本人が亡くなったあとに効力を生じる、意志表示です。
終活には様々な項目がありますが、気になっているという方が多いのがこの「遺言」についてです。
遺言は、主に遺産を巡った親族間の争いを防ぐために用いられるようですが、それだけではありません。
民法で定められているような相続は画一的なものが多く、一人ひとりの家庭事情に合わせるには限界があります。
その際に活用できるのが遺言です。用意をしておくと、本人だけでなく家族みんなの幸せのためになるのです。
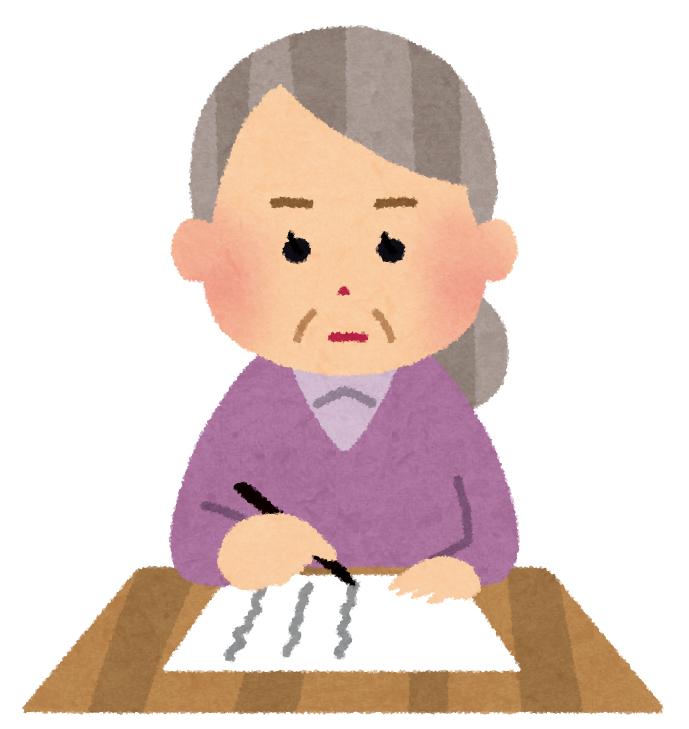
「ただの紙」から遺言書にするには
「『遺』す『言』葉」といっても、ただの言葉は効力を発揮しません。
基本的には文書で示され、法律で定められた条件を満たしている必要があります。
このように言うと、「難しそう」「自分ではできない」と思われるかもしれません。
しかし遺言をしたためた文書、つまり遺言証書にも種類があります。
いろいろな遺言書
- 自筆証書遺言(保証人が必要なく、自分で書くことができる)
- 公正証書遺言(公証人に依頼する)
- 秘密証書遺言(内容を見せずに公証人に依頼する)
一番簡単なのはやはり自筆証書遺言でしょう。いつでもどこでも、誰でも書くことが出来ます。
しかし安心の面ではどうでしょうか。この遺言書は自筆である必要があります。
でも本人が書いたものかどうかは、どうやって見極めればよいでしょうか。
また遺言書の保管場所は、限られた人にのみ伝えておきたいものです。しかし自分が亡くなった際、遺言書の所在が分からず発見されなければ、遺書の意味が無くなってしまいます。
対して確実性が高いのが、公正証書遺言と秘密証書遺言です。ただしこれらは、法律のプロである公証人が必要になります。そのぶん、費用や時間はかかってしまうということになります。
このように、どの方式にもメリット・デメリットがあります。自分に最もあった方式を選択するのが一番良いかと思います。
遺言として書けること
遺言には大きく分けて次の三種類の事項があります。
①相続に関するもの
- 特定の相続人に相続させない。
- 民法と異なった相続割合を決める。
- 遺産の分け方を決める。
②財産の処分に関するもの
- 相続人以外への遺贈、寄付など
③家族関係に関するもの
- 認知による親子関係の発生など
遺言書の例
遺言として様々な事柄が書けますが、ここでは「民法と異なった相続割合を決める」例をみてみましょう。
民法で定められた法定相続ではなく、本人が決めた割合で分配をする場合です。
法定相続
下の表は、民法に規定された法定相続人と法定相続分を示したものです。
| ケース | 相続人 | 相続分 |
| ① | 配偶者と子供 | 配偶者1/2 子供1/2 |
| ② | 配偶者と父母 | 配偶者2/3 父母1/3 |
| ③ | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
| ④ | 配偶者のみ 子供のみ 父母のみ 兄弟姉妹 | 該当者がすべて相続 |
しかし遺言では、法定相続と異なる財産分与が可能になります。また「この相続人に遺産を多く与えたい」「この相続人には与えたくない」など、ある程度自由な遺産相続が可能になります。
遺産相続に関する遺言書の例
遺言書
遺言者〇〇は、この遺言書により次のとおり遺言する。
一 遺言者は、全財産を次の割合で、次の者たちに相続させる。
一 妻□□に二分の一
一 長男××に十二分の一
一 次男△△に三分の一
一 長女☆☆に十二分の一二 この遺言の遺言執行者として、友人の※※を指定する。
〇年△月□日 遺言者〇〇 ㊞
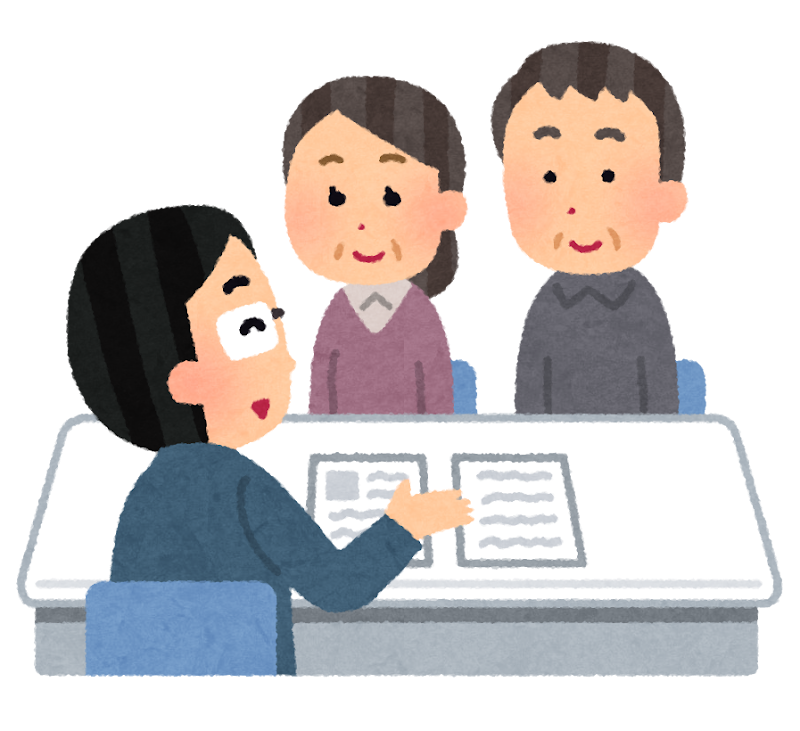
やっぱり自分だけでは不安…そんな時は
遺言書の種類や内容を知ると、「遺言=難しいもの」という印象も少し和らいできたのではないでしょうか。
しかし相続などといった家庭内の大きな問題を扱ううえ、人間関係や相続税の心配もある。
そのうえ遺言の効力が生かされるのは自分が亡くなったあと。やはり不安は尽きないものです。
そんな時は、相続や専門家に相談するのが一番です。
とっとり終活ホットラインでは、税理士、司法書士、行政書士などのプロとのネットワークが豊富です。
またワンストップサービスを活かし、遺書についてだけでなくお墓や家、お金の相談なども可能です。
お電話での無料ご相談も、お待ちしています。
お気軽にお問い合わせください。


